|
|
→町並み
→人物
|
|
↑上へ |
※昔と今の花車町地図を比較
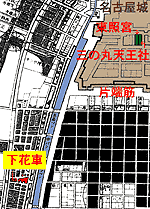
<江戸時代の下花車>
|
|
↑上へ |
| ここでは、山車を守り、維持し、動かす人々を紹介する。 約10年前まで、山車は町内の男性しか乗れなかった。(山車の綱を曵くことは、町内の女性にも許されている) しかし、少子化、高齢化による人手不足が予想されていたため、町内の女の子や、町外の男の子を囃子方として山車に乗せることになったのである。 <以下は永田氏の話を元に作成> |
山車に乗って祭り囃子を奏でる人。 メンバーのほとんどが子供で構成されている。お囃子はとにかく大切にされるため、長男(家を継ぐ=町に残る)が囃子方になっていた。 10年程前までは女人禁制だったが、少子化により現在は女性も多く活躍している。 |
 お囃子リスト |
||
|
紋付袴で参加。 |
||
山車運行の総責任者で、山車の一番前に立つ。江戸時代、唯一帯刀(切り捨て御免)を許された人。 |
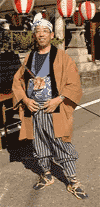  |
||
切師のまとめ役。綱割りの指示で山車が方向を変える際、その指示などは宰領が行う。 また、立ち切りやヤエマワシなどの時に扇子で切師をあおり、士気をあげる役目をしている。 立ち切り 切り師が梶棒をかつぎあげ前輪を上げて方向転換すること。 ヤエマワシ てこが後輪を固定し、切り師が勢い良く回転させること。 |
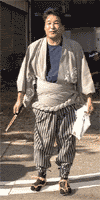 |
||
(人数は1人2人ではなく1枚2枚と数える) 山車の梶棒をかつぐ人。 今では祭りの花形だが、昔は港から荷を引き上げる人夫などを雇っていた。そのため、祭りの祝儀などはほとんど切り師の支払いに使われていた。 ある町では、切り師が遊廓に山車を曵いていき遊ぶ姿も見られたという。 切り師と呼ばれる由縁は、石切り職人からきている。 江戸時代石切り職人といえば力のある男の象徴であったのだろう。 衣装は『石』の模様であり、山車のかつぎ手を切り師という。 |
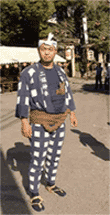 |
||
山車の車輪に『てこ』を入れて、山車をまわしやすくする人。 てこは山車の動きを左右し、また切師と息が合っていなければならないため、かなりの技術が必要となる。 |
|||
山車前部の綱で山車を曵く人。 二福神車の綱引きは、ほとんど女性で構成されている。 |
| ↑上へ |
| 戦前、戦後にかけて山車の保存は町内会(もちろん男性のみ)が行っていたが、祭当日は雇われた梶方が仕切っていた。 その当時、山車は名古屋駅方面(花車町西)や円頓寺周辺(花車北)まで曵き出され、祝儀を集めていたという。そのため山車は、『貧乏ぐるま』と呼ばれあまり歓迎されていなかった。花車町は下町のうえ世帯数も少なく町内に3つも山車があったことから、祝儀が町民から多くとれず隣町に頼ったと思われる。 現在も山車は町内会が保存している。この他、二福会という組織も関わり活動している。二福会は、将来の人手不足を考え、町内に住んでいない人にも祭りに参加してほしいという目的から設立された。 2001年度から、町内会にあった保存会が独立し『下花車二福神車保存会』が設立される予定。 山田良造氏(元町内会会長)談 |